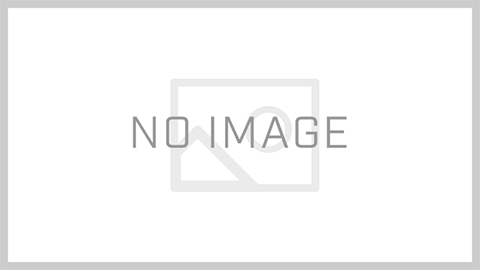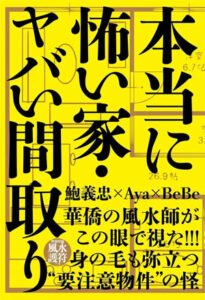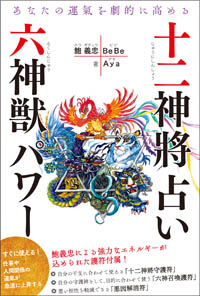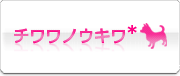お盆を迎えました。
一昨日の大雨で新幹線が運休となり、やむを得ず、東京から福岡への帰省の予定が変更となりました。
この日、大変なことになっているなんて全く知らず、お気楽に東京駅に向かった私たち姉妹とチワワのうきわは、新幹線の運行の見通しが立たないことを知らされ、そのまま改札前で1時間ほど足止めされたんです。
その後、ようやく予定の新幹線に乗り込んだものの、今度はそこから発車する気配がないのですよ。
するとやがて、「広島までで折り返し運転となります」というアナウンスが流れてきて、「……ってことは、博多まで行けないってことよね‼️」と、慌ててホームに降り、いったん引き返すことにしたのでした。
翌日改めて出直して、なんとか福岡まで戻ることはできたのですが、博多駅も驚くほどに大混乱となっていましたから、一日遅れてでも、とにかく無事に帰福できたことに感謝しました。
お盆の時期は、毎年のように何かしらのトラブルがつきものだとわかっているはずなのに、うっかり無謀なスケジュールを組んでしまいました。 この時期の移動は、やはりリスクが高いですね、反省です。

さて、こちらは先日訪れた深大寺の山門の写真です。
色鮮やかな「ほおずき」で飾られたゲートの傍には、「招福門・ハッピーゲート」と書かれた看板が立っていました。
この時期、深大寺の「ほおずきハッピーゲート」をくぐると、福を招くとされているのだそうですよ✨
「ほおずき」には、古くから魔除けの効果があるとされ、無病息災を願う縁起物として、玄関に飾ると、悪い運気を払い、良い運気を呼び込むといわれています。
そういえば、子供の頃に祖母の家に遊びに行くと、必ず玄関に、ほおずきの鉢が置かれていたことを懐かしく思い出します。
そ〜っと開いて、中からプチトマトみたいな赤い実を取り出して遊ぶのが楽しかったな。
ほおずきの実は、赤く色づけば色づくほど、魔除けの効果が高まるんですって。
また、咳止めや利尿作用、解熱効果があると言われていて、昔は薬草としても使われていたのだそうですよ。
ところで、「ほおずき」の英名は「 Chinese lantern(チャイニーズランタン)」で、漢字だと、「鬼灯」と書いて「ほおずき」と読みます。
そのまま読めば、「鬼火」という意味に受けとれそうですが、中国の昔の書物には、霊魂のことを「鬼」と記してあったりしますので、ほおずきの漢字は「霊魂の灯(あかり)」という意味なんですね。
赤い袋状の、提灯のような形をしているから、その見た目通りの名前が付けられているわけです。
そこでお盆の時期には、提灯みたいなほおずきを、ご先祖さまたちの魂が迷わず帰ってこられるようにと、道を照らす「灯火」として飾るようになったようです。
きゅうりやナスで作る馬や牛が魂の乗り物だとしたら、「ほおずき」は、その道を照らす灯りの役割を果たします。
地域によっては、お仏壇に吊るすご家庭もあるようですし、盆棚や精霊棚(しょうりょうだな)に飾るところもあるようですね。
お盆といっても、特にお墓参りに出かけたり、お盆の行事をなさるご予定のない方でも、ご先祖様のために、可愛らしいランタンのような「ほおずき」を飾ってみられてはいかがでしょうか。
今日もご覧下さってありがとうございます。
このバナーをポチっとクリックして、ブログのランキングアップにご協力くださいませ‼ 応援よろしくお願いします。